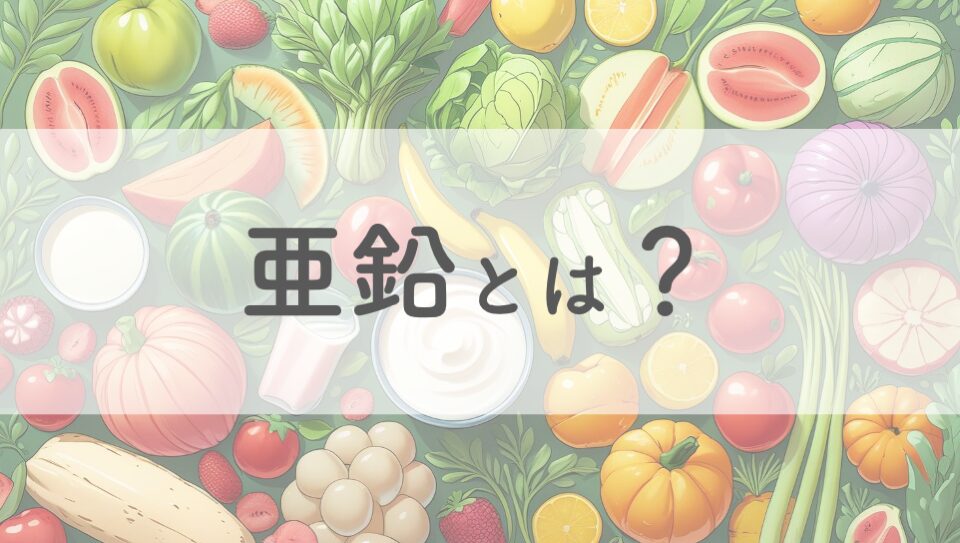
亜鉛:免疫から肌・味覚まで支える“万能ミネラル”
はじめに:亜鉛って、こんなに重要だったの?
「亜鉛」は人体にとって不可欠な必須ミネラルの一つで、免疫力、皮膚、味覚、ホルモンなど、さまざまな機能を支える重要な栄養素です。
成長期の子どもから高齢者まで、あらゆる世代で必要とされる“縁の下の力持ち”的存在。その働きと摂取のポイントを見ていきましょう。
亜鉛の主な働き
- 免疫機能の維持:細菌・ウイルスに対する防御力を高めます。
- 細胞分裂・DNA合成:成長や細胞修復に関わる基本的なプロセスに不可欠です。
- 皮膚の健康・傷の治癒:組織の再生や炎症の抑制に働きます。
- 味覚・嗅覚の正常化:味蕾や嗅上皮の機能維持に必要です。
- 生殖機能の維持:男性では精子の形成やテストステロン分泌に関与します。
どれくらい摂るべき?
日本人の食事摂取基準(2020年版)によると、以下が推奨量です。
| 性別・年齢層 | 推奨量(1日あたり) |
|---|---|
| 成人男性(18〜64歳) | 10 mg |
| 成人女性(18〜64歳) | 8 mg |
| 妊娠中(18〜49歳) | 9〜10 mg |
| 授乳中(18〜49歳) | 11 mg |
不足するとどうなる?
- 免疫力低下による感染症リスク増加
- 皮膚炎や傷の治りの遅れ
- 味覚障害(料理の味がわからなくなる)
- 成長障害(子ども)、精子数の減少(男性)
- 慢性的な下痢、食欲不振
摂りすぎも注意!
耐容上限量(過剰摂取で健康に悪影響が出ない最大量)は以下の通りです。
| 年齢 | 上限量(1日あたり) |
|---|---|
| 成人男性 | 40 mg |
| 成人女性 | 35 mg |
長期間の過剰摂取は、鉄・銅の吸収を妨げたり、吐き気や胃痛の原因となることがあります。
亜鉛を含む食品と吸収のコツ
- 動物性食品:牡蠣、牛肉、レバー、うなぎ、かつお、卵
- 植物性食品:納豆、豆腐、かぼちゃの種、ゴマ、ナッツ、玄米
植物性食品に含まれるフィチン酸は吸収を妨げることがあるため、発酵(納豆)や加熱を取り入れると効果的です。
豆知識:風邪の予防にも?
風邪やインフルエンザ対策として、初期に亜鉛を補給すると症状の持続時間が短くなるという研究報告もあります。あくまでサポートですが、バランスの良い食事と併せて意識しておきたいポイントです。
まとめ
亜鉛は、体の多くの働きを支える“マルチタスクなミネラル”。
免疫、皮膚、味覚、ホルモン、成長…と、欠かすことのできない栄養素です。
不足にも過剰にも気をつけながら、食品からバランスよく取り入れていきましょう。